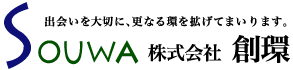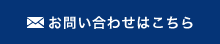社長ブログ
2022年今年も大変お世話になりました。
2022年も残すところあと僅かとなりました。早いものです。
コロナウイルスが出始めてもう3年が過ぎようとしています。たかが風邪とは言いたいもののその影響は多大なる被害を世界中にもたらしました。
当社もそのうちの一つです。イベントは延期、中止を余儀なくされ、飛躍を誓った2019年以降、逆に売上は下降線を辿るばかりでした。
今期においては経営戦略の見直しを余儀なくされ、10年計画で会社運営の立て直しを図らねばなりません。経営者にとって先を読むことの目は大事なんだと改めて知る機会となりました。願ってばかりではなく、自分で変えていくことの重要に気づけただけでも収穫はあったように思えます。
さて、そんな状況の中、当社に新たに2名の社員が加わりました。これからの活躍に大いに期待しています。
私は19歳で千葉のとある会社に入社しましたが、その時社長から一つの言葉をいただきました。
その会社の社長は新入社員一人一人に名前とリンクさせた名言を額縁に入った厚紙に筆書きして渡してくれます。
私には名前である’建一’の’一’に因んで「一日一歩 ローマは一日にして成らず」という名言をいただきました。
今になってこの言葉はとても響きます。会社の繁栄はまだ先のことであっても一歩づつ焦らずに続けていくことの大事さを改めて感じています。
そんな中、とある会社から座右の銘をフォトスタンドで差し上げますと言われたので迷わず作ってもらいました。
これを眺めながら2023年も頑張っていこうと思います。
2022を迎えて
2022年を迎えました。皆さまあけましておめでとうございます。
今年のお正月休暇は12月30日〜1月3日までとなりましたが、ホントあっという間ですね・・・。
その短さとは裏腹に、コロナ渦のトンネルはまだまだ先が見えない状況で、一体いつまでこのような状態が続いていくのか皆目見当もつきません。
何か策をと考えてみてはいるものの、この状況を打開するにはやはりインターネットを使った「何か別の商業」なのでしょうか。
当社は人との接点を大事に育ててきた会社です。対面することで相手のお客様に安心と信用を売ってきました。それが今このコロナ渦で対面はNGとされています。
「ニューノーマル」というような用語をよく見かけます。マスクをつけて、常に消毒をして、人数を制限して、相手に迷惑をかけない行動をとることが今後の常識となるのでしょうか?とても不安です。普通におしゃべりして、お酒を飲み、意気投合し明日を語り合ってたあの2年前が遠い昔のことに感じているのは私だけではないでしょう。時代は常に変動して行きます。企業もその変動に合わせ身を委ねるように変化して行きます。それは理解できます。
しかし、人はいつの時代になっても義理と人情、愛情と友情を忘れずに接していきたいものです。ガラス越し、モニター越しに写る相手はどうにも自分にバリアを貼られているようで好きになれません。
。。。と新年早々愚痴だらけの投稿となってしまいましたが、あれから2年、とうとううちの娘も中学生になりました。早いものです。
最近は娘とよく猫カフェに出かけます。マジで癒されます。この時ばかりは時間が止まって欲しいと切に願うのですが、無情にも2時間なんてあっという間です、、(笑
ステイホーム
新型コロナウイルスもようやく終息を感じ始めた今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
当社も2月初旬あたりから受注していた仕事の雲行きが怪しくなり、3月、4月の受注していた仕事は、ほぼ中止となりました。とても残念です。
しかしながらこのような未曾有な出来事が人生の中で起こることになろうとは夢にも思っていなかったわけで、本当に平和というものをあらためて考えさせられる事象になったと思っています。1日も早く以前の日常が戻ってくれることを望みます。
さて、当社も4月20日から本格的な自粛モードになりました。私は残務整理があったため、5月2日から連休としましたが、今年の連休は「ステイホーム」とのことなので全くウキウキしない連休となってしまいました。仕方ないので、5年ほっぽり投げていた庭の整備に取り組んでみました。ちなみに庭で使っている木材等は全て現場から引き上げてきた廃材です。(笑
まずこの写真がbefore。
福井県の旅
福井県国体の建物申請業務に携わりました。当社はクレー射撃場、バトミントン、ソフトボールの3つの会場に設置する大型テントの申請業務を担当したのですが、福井県なんて生まれてはじめて踏む土地でもあります。福井県の特徴はどうやら恐竜の化石の宝庫だということで駅前からいたるところに恐竜の模型が設置されています。そんな中で会場の近くに越前大仏なるお寺があったのでご利益を兼ねてお参りしてきたのですが…。

がら〜ん…。
見事なまでのシャッター街と化していました。

どうやらここのお寺は大阪のタクシー王と呼ばれるタクシー業界のドンこと多田清氏が生前に慈善事業として380億円もの自分の財産をなげうって建立したということのようです。一世一代でこのような建築物を世に残すなんて…、きっと、ロマンに溢れた人物だったのでしょう。

福井県のお寺と言えば永平寺が特に有名ですが、なんというかこちらのお寺は外国人旅行者さえもおらず、まるで貸切状態です。もっとも、私は人ごみが嫌いなほうなのでこの状況はむしろ大満足なわけですが…(笑
本殿の奥には日本一の高さを誇る越前大仏が鎮座しています。

境内の中には五重塔もそびえ立っていて、勝山市の風景を一望でき、とてもいい眺めでした。
(ちなみに遠くに見えるお城も多田清氏が建てたお城です。)
なにはともあれ、人生のうちに形ある何かを残すということは情熱とロマンに満ち溢れていて、私自身これからの人生にとても共感させられる想いがあります。今回のお仕事をくれた佐賀県の大和産業さんに感謝です。
とてもよい旅路になりました。(あ、、、申請業務の仕事もしっかり終わらせましたのでご安心を・・)(笑
エビ
今年の夏は東海地区の高校総体、福井県国体と、二つのイベントの建築物申請業務を行いました。
その為、月10日位くらいは新幹線に乗って東海地区、中部地区を駆け回る日々でしたが、
やはり、見知らぬ土地で仕事することはワクワクするものでもあります。(私だけかもしれませんが…)
ともあれ、これは名古屋で見かけたエビです。長さは40cm以上、太さは缶コーヒーのスリムボトルくらいあります。
もはや、ウルトラマンにでてくるような怪獣そのものです。こんな食事に出会えるのも旅路の楽しみの一つですね。
気がつけばもう3年目

学校の運動会に参加しました。
気がつけばPTA会長を務めて3年目となってしまいました。(汗
月日が経つのは早いものですね、、。PTAってなんぞや?というくらい何の理解も知識もなかった私ですが、今ではすっかり飼いならされて?(笑 PTAは必要不可欠と言い切ってしまうまで成長した自分がいます。
こうやって3年前の自分と今の自分を見比べてみたときにはじめて、あのときの選択は人生の分岐点の一部だったような気がします。
PTAを知ることないままの自分。
PTAを知ることができた自分。
今では、学校、地域の方々とも懇談したり、他の学校の会長さん達とお酒を飲んだりして理解を深め合っています。いろんな意味でやってよかったと思っています。まだまだ至らないところはたくさんありますが、今年も精一杯頑張らせていただきます。 ^^b
ちなみに写真は大玉ころがしの判定員として立っているのですが、ただの晒し者です(笑
春うらら

お花見の季節が終わり、ゴールデンウイークに近づいてまいりました。
4月27日からお台場で開催される”肉フェス”のイベントの申請業務のお手伝いしました。とても人気の高いイベントです。
今年は珍しく5月の連休に仕事の予定がなかったので、娘とイベントに参加してみようと思っています。^^b
働くということ

Googleさんのオフィスにおじゃましました。(^ ^)
と言うのも、たまたまPTAでの知り合いに社員さんがいらっしゃってランチのお誘いを受けることに。
(Googleマップでおなじみの全方向カメラ。全て車からの映像と思っていたのですが、人力とか三輪車も...。)

Googleオフィスは何かの記事かTVである程度知っていたのですが、目の当たりにしてみるとやはりユニークですね。
ここは日本なので、部屋名が山手線だったり、植物、フルーツの名前だったり、フロアのイメージも廊下からお部屋まで一貫して装飾がされており、「日本」をキーワードに様々な工夫がこなされていて、日本を感じながら働けるスペースになっているのです。(温泉旅館をイメージしたスペースや暖簾をくぐる打ち合わせ室とかもありましたよw)

こんなお部屋もあったり...。(音楽を自由に楽しめるスペース)
壁にはたくさんのギター、ピアノ、マイクなどなど楽器の種類も豊富に取り揃えてありました。
ああ、人生やり直せるならちゃんと英語勉強しておくべきだったよ...。(笑

何よりも驚くべきことの一つは、オフィス内にあるビュッフェ形式の食堂(しかも、3ブース)コーヒースタンド、自動販売機の飲み物まですべて無料で提供され
しかも「うまい!」(遠慮しがちな盛り付けですが、食べ放題なので焦る必要もない...)
コーヒーにしてもデザートにしても全てが手抜きなし。朝から夜まで提供されているそうで、いつどのような時間でも利用可能とのこと。もはや楽園です。(笑
オフィスで働く人たちの雰囲気もすごく自由で活気に満ち溢れていました。たしかに、息詰まった環境では良い”アイデア”は生まれません。成果に期待するなら、まずは環境からということなのですね。
今回オフィスに招待してくれた、某PTAの⚪️⚪️さん!
今日は本当にありがとうございます。
”働く”という意味を改めて考える良い機会になりました。(^ ^)
出来ることなら今度はお仕事でお邪魔したいですよ!
(毎日、六本木の町並みを見下ろしながら食事できるなんて、羨ましすぎる...。)
信じるものは救われ…る?

今年も行ってまいりました穴八幡宮。
昨年は節分前ギリギリの参拝でしたが、今年は余裕を持って行くことに。

赤い鳥居をくぐり、階段を上ってみると…
・・・・・。
この並びの数に心を折られ一瞬帰ろうかと思ったほどでしたが、やはりこの苦行を乗り越えて初めてご利益があるのだと勝手に妄想し、修行のつもりで参列することに。

並ぶこと1時間半。ようやく本殿に到着。お札と一陽来復御守、幸運の巾着袋を購入しお参りしてきました。
私自身、神様というものにはあまり深い信仰心はないのですが、やはり信じるものは救われる?のでしょうか。
事実、昨年の資金状況を鑑みてみると常に安定していたようにも思います。これをご利益と考え、深く感謝を込めて
今年もどうかご利益がありますように・・・。(ー人ー)
2018年ご挨拶
新年明けましておめでとうございます。ブログを更新しようしようと考えている間に2018年を迎えてしまいました。(汗 昨年は年男ということもあり、すばらしい運が巡ってくることを期待し弊社一同強い気持ちでいろいろな業務にチャレンジしてまいりました。
おかげさまで新規業務並びに取引先、そしていろいろな人との出会いが例年以上に増え、大変嬉しく思っております。
当社をご愛顧いただいた皆様、本当に有難うございました。2018年も同じ気持ちで弊社一同頑張ってまいりますのでどうか引き続きご愛顧いただけますようよろしくお願い申し上げます。
可愛い子には旅をさせる?
子供が夏休みに入りお盆間近という今日この頃、娘が一人で中国に旅たちました。
もっとも搭乗する飛行機のサービスとして、子供の受け渡しから、お引取りまでの面倒は見ていただくのですがなんというか自分が子供の頃を想像すると一人で飛行機に乗るなんて到底考えられなかったことで...
もっとも娘にしてみれば中国にいる義兄弟との再会の方が不安な旅路より気持ちは上なのでしょうけども。
にしても,,,可愛い子には旅をさせろなんて昔からよく言われていますが、本人の気持ちとは裏腹に親の気持ちとしては不安以外ないですね。まあ、向こうでの生活のほうがいいと駄々をこねないことを期待して、待つことにします。
三浦海岸海の家
オファーハウスbyLINEバイト海の家

2月の節分からブログ更新を怠っていましたが気づけばもう夏です!
夏といえば当社の決算期でもあり事業報告をせねばなりません。今季の反省と来期の抱負を考えるだけでも頭痛いです...。
まあそれはさておき、今年久々に海の家をプランニング、施工をいただけることになりました。
今回の趣旨はLINE機能を使ったオファーで作る最強の海の家を展開することだそうです。
プランニングからパース作成までざっと2ヶ月、施工開始が7月1日。引渡しが7月13日とかなりハードな内容で展開することになってしまいましたが、追い詰められるとなぜか別の何かが目覚めてしまうSOUWAでもあります。

建物のイメージは西海岸風ということで、木材を多量に使用した海の家となりました。はじめは背の高いプレハブ構造で考えていましたが、時期的にプレハブのレンタルは完売とのことで、代替えとしてユニットハウスを選択しました。ユニットハウスは一つのハウスに換気扇、コンセント、照明が備わっており、もちろん天井も綺麗に仕上がっている為、電源さえ入れば即入居可能なところが売りです。時間のない設定にはもってこいの素材でもあります。

白で着色しました。どうです?もうここは西海岸ですよね?(笑

海の家のバイトに関わった人を写真にして飾っています。なぜかこの中に私の姿も...(もちろん会長に内緒でバイトはしていませんよ?

今回お世話になったクライアントのLINEの皆様、そしてこの仕事の発注者である(株)凌芸舎の窪島社長様はじめ社員の皆様、絵を描いてくれた亜美さん、そしてSOUWAに協力してくれた協力業社の皆さん、本当に皆様とともに過ごした2週間は思い出深いものとなりました。今後ともどうかお付き合いのほど宜しくお願いいたします。
あっ、そうそう、せっかくなのでオファー機能を使ってSOUWAも人材募集しておこうかな... 割と本気で...(笑
これは趣味ですが...
弁当だってお任せ!

昨今の小学校は弁当を作る機会も結構多いですね。
当社SOUWAでは弁当だって作れちゃうんです!(完全な趣味ですが...)

重箱だってご用意いたしますよ!
穴八幡宮
穴八幡宮に行ってきました。社内の新年会で当社の叶内顧問から2月3日までにお札をもらってくるようにと頼まれていたのをすっかり忘れていました。(汗
今日は税務署の調査日だったのですが、許しを得てなんとかもらってきたのですが、実際どのようなご利益あるのかは全く理解していないまま、参拝をしてきたのですが、境内には「一陽来復」なる文字をやたら見かけたのでネットで検索してみました。ここからはその引用になりますが、、、
一陽来復とは
旧暦では、冬至を含む月が十一月にあたり、その前の月が十月になります。
易経では、六個の陰と陽で、月(季節)を現します。図で表すときは、中央が白く抜けている横棒が“陰”、黒い横棒が“陽”です。
十月は「坤為地(こんいち)」で、六個全てが陰になる月です。

そして、冬至を含む月である十一月は「地雷復(ちらいふく)」になり、陽が一つだけ現れます。

陽が一つ現れることから、「一陽」になり、“陰極まれば陽に転ずる”を表します。
そして、太陽の力が回復して来ることから、「来復」となり、「一陽来復」となります。
(来復を来福と書く社寺もあるようですが、本来の意味では来復になります)
一陽来復は、ターニングポイントであり、陽が現れることを意味するので、解釈は以下のようになります。
| ・これまでの、陰が支配的だった季節は終わり、陽に向かう ・これ以上悪くなることはなく、良い方向に転じて行く ・これまでの苦労は、かならず報われる ・この先には、何の障害もないので、安心して進んでいけばよい |
この一陽来復のエネルギーをお金に適用したのが、早稲田穴八幡宮で冬至に頒布される一陽来復御守です。
なるほど。。。。よくわからん。
穴八幡宮の冬至祭
江戸城北の総鎮護である穴八幡宮(あなはちまんぐう)では、江戸時代から続く、金銀融通の「一陽来復(いちようらいふく)」御守を冬至から節分までの期間に授かる事ができます。 この御守を恵方に向けて高い場所にお祀りするとお金繰りが良くなると言う事で大変な人気があります。冬至の日が休日と重なると、授かるには数時間待ちになることもあります
ということで、買ってきたお札と、きんちゃく袋に祈りを込めて
「お金繰りが良くなりますように!!」
グルメンピック2017
今朝Ipadのニュースを読んでたところ、グルメンピック2017の記事を見つけました。
どうやら、詐欺ではないか?ということで世間で取り上げられているみたいですね。
当社も過去何度か食に関するイベント設営業務に参加したことはありますが、とにかく規制が多く、万全の準備が必要となります。消防法、保健所、仮設申請等々、特に食に関する保健所の指導は厳しく、条件によっては調理されたものを温めるだけというようなことにもなります。
なので、お店で食する”うまさ”だけを比較するととてもおいしさを感じ得るイベントにはならない気がします。だからB級だとかそういうイベントが多いのです。
また、食のイベントを開催するときは、基本はユニットハウス。テントは不可。しかも内装は消防による指導が入るため防火仕様に改造しなければなりません。そして食品の受け渡しも制限がつきます。基本は窓を閉めるとか、仕切りを垂れ下げるとか・・・。
そして何よりも、開催される場所はなるべく無償で借用できるところを探すことに尽きます。当社が大阪で参加した食のイベント開催場所は万博公園でした。大体、食のイベントとなると公園が多いはずです。
そういう条件下で1店舗20万?300店舗参加としても、6000万程度でこの企画は不可能です。相当数のスポンサーのバックアップが必要でしょう。
まあ、そういった事情を知らない出店者は”食のオリンピック”に釣られてぜひ参加をしたくなるのでしょうけど、そういった心理を悪用してますよね・・・これ。
この企画、味の素スタジアムで開催らしいのですが、一般の人たちにはスタジアムの中で開催されるようなイメージしてしまいますよね・・・。
味の素スタジアムは陸上競技場です。中での開催はきっと無理です。もし行うとしたら、国を挙げてのイベント規模になるでしょう。まして、イベント実績もない平成25年度設立の会社がこのようなBIGイベントをこなせるはずもありません。訴えをおこしていないから、まだ詐欺事件にはなっていないのでしょうけども、これは明らかに出店者側の心理を突いたプロの犯行です。過去このようなイベントを実際やったことのある経験者なんでしょうね....。
今年の抱負
今年は酉年にちなんで”飛躍の年”という位置づけで業務を進行してまいります。
まずは、社員を1~2名補てんする意味で、みずほ銀行から運営資金の調達を行いました。
業務は営業活動と施工管理になります。男女どちらでもかまいません。興味ある方がいらっしゃったらご一報ください。当社会長が面接いたします。
また、新事業として当社で取り扱っている”フレックスタフ”の販売を進めていきたいと思います。
フレックスタフとは、去年アメリカでライセンス契約をしてきた塗材です。成分はウレタン樹脂系ですが非常に摩耗に強く、しなやかで割れません。防水効果、保護膜としての効果が期待できます。
日本にもウレタン塗材は数多くありますが、この性能を満たすものは存在しません。ゆえ、当社はこの販売に力を注いでいきたいと考えています。
鉄、コンクリートはもちろん、陶器、布、スポンジにも何にでも塗膜でき、アメリカではゴムボート船底、ソフトマットを使用したウォータースライダーなどの塗膜に使用されています。
この塗材の可能性を日本で広げるため、まずは建築建材を軸にサンプルの作成を行っていきたいと思います。ご興味ある方は当社までご一報を!
PTA活動
PTA活動を通じて
一昨年、突然娘の通っている学校からPTA会長職の打診がありました。会長の伊藤から「世間の様を身近で見る良い機会だから承諾しなさい」と背中を押され承諾したのですが、あれから一年が過ぎようとしています。
PTA活動を通じて感じたことといえば、”ボランティア精神”の一言に尽きます。
ボランティアゆえ、責任の所在がはっきりしません。また、強制もできません。しかし、会費を集めて活動を運営していくスタイルはちょっとした会社並みの業務が付きまといます。それをすべて”ボランティア”という名の元で活動をしています。
会長の業務と言えば、活動の承認と他校PTA会長との会合ぐらいで、他の委員さんに比べるとまだ楽なほうだと思われますが、いままで学校教育には背を向けて生きてきたせいか、日常でこのような活動を献身的に行っている保護者様(奥様)には感心しきりです。
昨年会長業務として唯一記憶に残るものがあるとすれば、学校祭に区のゆるキャラを呼んであげたことぐらいでしょうか(笑)
今年も継続してPTA会長を務める意志ではありますが、無限のスパイラルに捕まった気がしてなりません。(汗)
2017年開幕
新年のご挨拶
関係各位の皆様、新年あけましておめでとうございます。
昨年は東京都様、(株)関電工様、(株)関工ファシリティーズ様をはじめ、数々の案件を頂きまして誠に感謝しております。また、各案件に対応し、ご協力いただいた関係業者の皆様本当にありがとうございました。
まだまだ未熟ではありますが、社員一同今年も全力で業務に取り組んでいく所存です。どうか引き続き当社創環をご愛顧いただけますよう、よろしくお願いいたします。
乙酉(つちのととり)
自由人?
元旦早々からスキーに行ってまいりました。まったくのノリと思い付きで30日飲んだ席で決定しました。
今年は下の娘と妻が中国で正月休暇を過ごしていたため、残された私と上の娘とアメリカから一時帰国した妻の知り合いの3人で当日レンタカーをチャーターし、新潟県湯沢にある神立高原スキー場へ。
今年は雪が少ないとの情報もあって少々不安はありましたが、トンネルを超えるとそこは雪国でしたよ。(笑)
関東になじんでしまったせいか、目に映る雪の白さが非常にまぶしく、心が洗練された思いでした。(決して心がくすんでいるわけではありませんのであしからず!)
今年は酉年ということで、私は年男です。
1969年生まれの酉は、乙酉(つちのととり)というそうですが、ちなみに特徴はというと・・・
この生まれの人は、野鶏といいます。自然のままに育つ鶏で、種類は家で飼われる鶏と同じですが自由です。したがって食には不自由が多い。人に養われても、すぐに飛出してしまいます。外出好きで、遊び廻る癖があり、家におちついていられません。華美を好み、演芸など陽気なことが好きで、寂しがり屋です。物忘れが多く、経済的観念に乏しい人です。
だそうで・・・当たってるだけに反論の余地がありません。(笑)